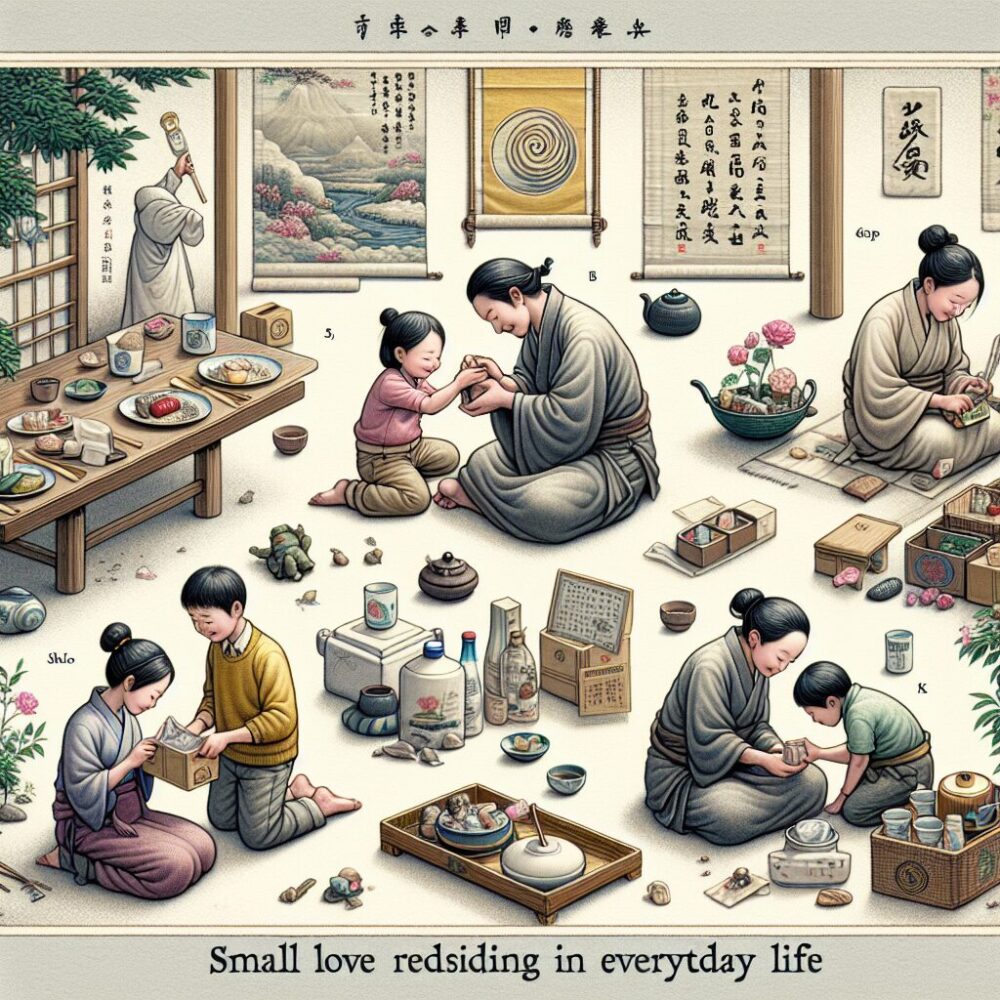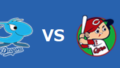やあ、諸君。紫煙亭のカウンターへようこそ。
秋であれば夜長に燻らせる一服は、いつもより深く、そして長く、思索の伴走者となってくれる。
前回、第七夜では「自己愛」と「セルフコンパッション」について語った。自分自身を慈しみ、その存在をまるごと認めてやること。それが、他者を、そして世界を豊かに愛するための、いわば第一歩であると。コップの水が満たされていなければ、他人の渇きを潤してやることはできないからな。
さて、自らのコップを満たす術を心得た我々は、次なる扉を開くときが来たようだ。今宵のテーマは、我々のすぐ足元に、日常の風景の中にひっそりと息づいている「愛」についてだ。そう、「愛」とは、ラブソングの歌詞や壮大な物語の中だけに存在するものではない。むしろ、日々のささやかな営みの中にこそ、その本質が宿っているのではないかと、亭主は思うのである。
見過ごされる「愛」のかけら
朝、顔を合わせた同僚にかける「おはよう」の一声。コンビニで商品を渡してくれた店員への「ありがとう」という言葉。後ろから来る人のために、ドアを少しだけ開けて待ってやる心遣い。
どうだろうか。あまりに当たり前すぎて、意識にすら留まらない行為かもしれない。これらを「愛」と呼ぶのは、少し大袈裟に聞こえるだろうか。しかし、亭主はあえてこれらを「小さな愛」と呼びたい。なぜなら、これらの行為の根底には、相手の存在を認め、その瞬間を慮るという、温かい眼差しが存在するからだ。
我々は、知らず知らずのうちに、こうした無数の「小さな愛」に支えられて生きている。そして、我々自身もまた、誰かにとっての「小さな愛」の送り主となっているのだ。その事実に気づくだけで、日々の何気ない風景が、少しだけ違って見えるのではないだろうか。
「やらない善よりやる偽善」を超えて
とはいえ、いざ行動しようとすると、我々の心には妙なブレーキがかかることがある。「偽善者だと思われたらどうしよう」「自己満足に過ぎないのではないか」。そんな内なる声が、我々の足をすくませる。
よく「やらない善よりやる偽善」という言葉を耳にする。亭主は、この言葉に一定の真理があると考えている。たとえ動機が「よく見られたい」という下心であったとしても、その行動が結果として誰かの助けになったのなら、それは紛れもない一つの「善行」だ。行動だけが、現実を動かすのだから。
そして、ここからが重要なのだが、そうした「偽善」の行いも、繰り返すうちにやがて血肉となっていくものだ。最初は気恥ずかしく、どこか演技めいていたとしても、感謝の言葉をかけられ、相手の安堵した表情を見るうちに、行動そのものに喜びを見出すようになる。利己的な動機から始まったはずの行為が、いつしか自然な「利他」の心へと昇華していく。そのプロセスこそが、人間性の成熟というものではないだろうか。偽善を恐れて何もしない人間よりも、偽善とそしられながらも行動する人間の方が、よほど「愛」に近い場所にいると、亭主は思うのである。
「ケア」という温かい眼差し
ここで「ケア」という言葉について考えてみたい。我々は「ケア」というと、介護や看護といった専門的な行為を思い浮かべがちだが、その本質はもっと普遍的なものだ。それは、他者の状況に心を寄せ、その苦しみや喜びに寄り添おうとする「温かい眼差し」そのものと言えよう。
疲れた顔をしている友人に「大丈夫か?」と声をかける。重い荷物を持つ老人を見かけ、手を貸そうかと考える。それらすべてが、広義の「ケア」なのだ。それは、相手の苦しみを完全に取り除く「抜苦」には至らないかもしれない。しかし、あなたのその眼差しは、「私はあなたの存在に気づいている」という強力なメッセージとなる。現代社会が抱える「つながっているのに孤独」という病理への、ささやかな、しかし確かな処方箋だ。
前回語った「セルフコンパッション」が自分に向ける慈しみの眼差しだとするならば、「ケア」とは、その眼差しをそっと他者へと向ける行為に他ならない。
さあ、君の「小さな愛」を教えてくれ
壮大な「愛」を追い求める前に、まずは我々の日常に散りばめられた「小さな愛」に気づき、そして実践してみることだ。自分を慈しむように、隣人を少しだけ気遣ってみる。そのささやかな実践の連鎖が、我々の生きるこの世界を、もう少しだけ温かい場所にしてくれるはずだと、亭主は信じている。
さて、今宵はこの辺りで一区切りとしよう。
今宵はちょっと口調が偉そうでありましたな。