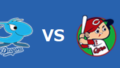全ての「つながり」の原点、それは内なる自分
紫煙をくゆらせながら、窓の外の喧騒に目をやる。SNSという蜃気楼、失われた地域の囲炉裏、そして家族という最小の他人――。これまで我々は、絶えず移ろいゆく「他者」との関係性の中に、「つながり」の在り処を探してきた。だが、どうやら大事な視点を忘れていたようだ。外へ、外へと向かいがちだった我々の視線を、一度、内側へ、つまり自分自身の深淵へと向けるべき時が来た。前夜、私は「家族もまた最小単位の他人」と語り、血縁という絶対的な関係性の中にさえ、敬意と距離が必要だと説いた。そして、社会の中で我々が被る「役割」という仮面の話を予告した。だが、その仮面の下にある「本当の顔」とは、一体誰の顔なのだろうか。貴方は、貴方自身の顔を、その素顔を、きちんと見たことがあるだろうか。
自分は「探す」にあらず、「掘り起こす」ものなり
巷には「自分探し」という軽薄な言葉が溢れている。まるで、どこか遠い異国の地に、あるいは特別な体験の中に「本当の自分」が落ちていて、それを拾いに行けば見つかるかのような物言いだ。だが断言しよう。そんなものは幻想だ。自分とは、探すものではなく、掘り起こすもの。貴方が今いるその場所、その心の奥深くに、ただ静かに埋まっているものなのだ。
「汝自身を知れ」――他者理解は自己理解から
古代ギリシャの哲人ソクラテスは「汝自身を知れ」と喝破した。二千年以上もの時を超え、この言葉は情報の大洪水に溺れる現代の我々にこそ、重く突き刺さる。我々は日々、他人の成功譚や煌びやかな日常、社会が求める「あるべき姿」を浴び続け、いつしか自分自身の声を聞き分ける能力を失ってはいないか。何が食べたいのかではなく、SNSで「映える」のは何か。何がしたいのかではなく、他人にどう見られるか。その思考の末にあるのは、空虚な自己満足と、決して埋まることのない渇望だけだ。「汝自身を知れ」とは、己の長所や短所を履歴書のように書き出すことではない。自分が何に心を震わせ、何に静かな怒りを覚え、何に涙するのか。その感情の源泉を、澱んだ川の底を浚うように、辛抱強く探り当てる作業に他ならない。なぜなら、その源泉に触れることなくして、他者の心の渇きを真に理解することなど、できはしないのだから。己の痛みを知らぬ者が、他者の痛みに寄り添えるはずもない。
孤独を恐れるな、豊穣なる「Solitude」を味わえ
現代人は孤独を病的に恐れる。一人の時間を「寂しいもの」と断じ、スマホの画面に映るかりそめの「つながり」で懸命に空白を埋めようとする。だが、思い出してほしい。「孤独(Solitude)」と「孤立(Isolation)」は全くの別物だ。他者から切り離された状態が「孤立」であるならば、「孤独」とは、自ら選び取る、豊かで創造的な時間である。恐れるな、と言いたい。一日、いや数時間でいい。全てのデバイスを切り、静寂の中に身を置いてみてはどうだろう。最初は落ち着かず、手持ち無沙汰に感じるかもしれぬ。だが、その沈黙の先に、普段は喧騒にかき消されている微かな内なる声が聞こえてくるはずだ。それこそが、貴方自身の声だ。
日常に潜む「内なる対話」の作法
何も、山に籠って座禅を組めというのではない。内なる対話の作法は、ごく日常的な営みの中にこそある。例えば、日記を付けてみるがいい。誰に見せるでもない、自分だけの言葉で、その日感じたことをありのままに書き殴る。整理されていなくていい。格好つける必要もない。その乱雑な言葉の断片にこそ、貴方の本心が隠れている。あるいは、ただ目的もなく近所を歩いてみる。いつもの道も、速度を変え、視点を変えれば、新たな発見があるだろう。道端に咲く名も知らぬ草花、風の匂い、遠くで聞こえる子供の声。五感を解放し、思考を自由に漂わせる中で、ふと、凝り固まっていた問題への答えが見つかることもある。
揺るぎない根を張り、次の問いへ
己とつながる、とはそういうことだ。特別なことではない。自分自身に、丁寧に向き合う時間を持つという、ただそれだけのこと。自分という大樹の根が、いかに深く大地に張っているかを知ることだ。その揺るぎない根があって初めて、我々は他者という枝葉と健やかにつながり、風雪に耐え、豊かな実りを結ぶことができる。
さて、貴方に問おう。
最後に貴方自身の声を聞いたのは、いつだったか。
他者の評価という鏡ではなく、己の魂という水面に、自らの顔を映しているだろうか。
まずは、己とつながれ。全ての旅は、そこから始まる。
…さて、己の内なる声に耳を澄ませたならば、我々はその声をもって、社会という舞台でいかなる仮面を被り、いかなる役割を演じるべきなのか。次回は、その仮面の下にある「本当の顔」と、社会との間に生まれる「つながり」の力学について語ろう。