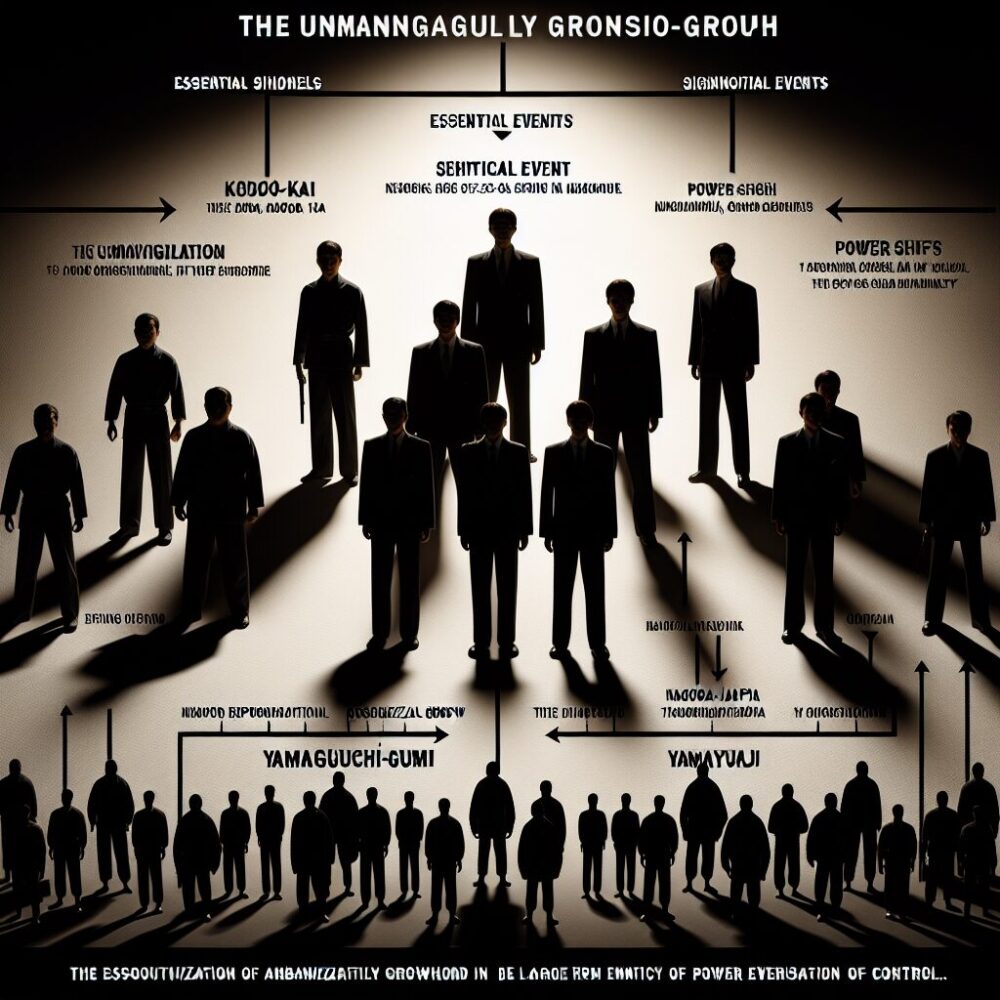皆様、ご機嫌よう。紫煙亭主人でございます。
現代は様々な情報が溢れておりますが、中には知られざる世界の深奥に迫るような動画も散見されます。本日皆様にご紹介いたしますのは、YouTubeチャンネル**「闇と光」さんがお届けする「【ヤクザ】弘道会が名古屋を統一し、山口組を掌握するまでの軌跡【起源である鈴木組〜名古屋支配】」**と題された一本。名古屋という地に深く根を下ろし、ついには日本最大規模の組織の頂点へと駆け上がった弘道会の歴史を紐解く、大変興味深い内容でございました。亭主も拝見し、その壮絶なる軌跡に唸らされた次第でございます。
始まりは「鈴木組」から – 名古屋の港と山口組との縁
動画は、弘道会の源流が「鈴木組」にあることを語り始めます。1960年代、中京地区には瀬戸一家、平井一家、稲葉地一家など、名だたる組織が地盤を固めておりました。その頃、鈴木組を率いていた鈴木光代氏は、名古屋港湾の船内荷役を一手に取り仕切っており、山口組直参の打越会会長、打越忍氏と兄弟盃を交わしておりました。その威光か、山口組三代目組長、田岡一雄氏からも舎弟盃を受け、鈴木組は山口組直参となったとのことです。
ここに、後に弘田組、そして弘道会の礎となる人物が現れます。高知県出身の広田武志氏でございます。彼は若い頃より大阪で港湾荷役に従事しておりましたが、1952年頃に名古屋へ移り住み、鈴木組に加入いたしました。別の話では、もともと鈴木組の者であり、組の名古屋進出に際して港近くの赤線地帯を縄張りにし、後に港湾事業に進出したとも言われております。
鈴木組の解散と「弘田組」の誕生 – 頂上作戦の余波
しかし、時代の荒波は容赦なく押し寄せます。1963年に発生したひろしま抗争を受け、警察は山口組に対し頂上作戦を決行。田岡一雄組長をはじめとする山口組の大幹部が次々と逮捕される事態となりました。危機感を抱いた田岡組長は、港湾荷役に関わる全ての者を山口組から離れさせる指示を出します。鈴木組もこの指示に従い、1966年に解散いたしました。
ここで、鈴木組の残党を引き受けたのが、鈴木組若頭であった広田武志氏でございます。彼は田岡組長から直々に親子の盃を受け、子分となり、山口組直参として「弘田組」を組織いたしました。
司忍氏の台頭と弘田組「武闘派三羽ガラス」
弘田組において、後に極道社会の頂点を極める人物が頭角を現します。現在の六代目山口組組長、司忍氏でございます。司氏は20歳で名古屋に移り、弘田組に入りました。組内でめきめきと頭角を現し、自らの組織「司興業」を結成。1968年には、当時「金持ちヤクザ」として知られた稲葉地一家の縄張りである歓楽街、中村区大門地区に事務所を構えたといいます。
弘田組には、司氏を含め、その武闘派ぶりで名を馳せた三人の幹部がおりました。弘田組若頭に就任した司忍氏、若頭補佐兼佐々木組組長の佐々木康宏氏、そして同じく若頭補佐兼神谷組組長の神谷光男氏でございます。この三名が、後に弘田組武闘派三羽ガラスと呼ばれ、抗争時には先頭に立って動いたとのことです。
相次ぐ抗争 – 弘田組の武勇
この頃の中京地区は、山口組とその勢力を二分する大日本平和会などが覇を競う、まさに火薬庫のような状況でありました。弘田組もまた、いくつかの血腥い抗争に巻き込まれていきます。
- 山中組との抗争 (1969年)
大日本平和会系の山中組小牧支部に立ち入りしていた男が弘田組系神谷組に加入したことが発端でございます。山中組長、山中健夫氏の指示により、神谷組事務所が襲撃され、神谷組員2名が亡くなり、2名が重軽傷を負いました。報復を計画する弘田組でありましたが、山中組側が襲撃犯を警察に自首させ、事務所を撤退させたため、報復相手を変更せざるを得なくなります。 - 豊山一家への報復襲撃
報復相手として標的となったのは、同じ大日本平和会系の春日井市の豊山一家でございました。弘田組系の司興業と佐々木組が豊山一家組長、砥山黄色氏を襲撃し、その命を奪いました。この事件により、首謀者として司忍氏に懲役13年、実行犯として佐々木組の高山清司氏に懲役4年などが言い渡されました。現在の六代目山口組若頭、高山清司氏はここで名を上げたと言えるでしょう。 - 稲葉地一家・鬼木会との抗争 (1981年)
1981年9月、鬼木会組員と海運会社社員との交通事故が発端でございます。稲葉地一家の過激派として知られる鬼木会が海運会社を襲撃。この海運会社の社員が広田組長の息子の同級生だったため、広田組に相談していたそうですが、同年7月に三代目山口組組長田岡一雄氏が亡くなったため、喪に服していた弘田組はすぐには報復できませんでした。それを逆手にとった鬼木会は、なんと弘田組事務所を銃撃。これに激高した弘田組は、鬼木会や同じ稲葉地一家系の杉田組事務所を銃撃し返しました。抗争激化を懸念した地元の親分衆は、運命共同会総裁の川澄正照氏を仲介人に立て、両組織の手打ちを成立させたとのことです。 - 同友会系ハマケン組との抗争 (1981年)
同じ1981年、街中での司興業と同友会系ハマケン組組員同士の喧嘩が発端でした。当時の同友会は愛知県下最大の組織であったといいます。喧嘩の謝罪に向かった司興業の組員が、相手事務所内で暴行を受けたことで事態は悪化。この事実に黙っていられなくなった弘田組組員が、金沢市の同友会系さかばやし組を襲撃し、重軽傷者2名が出ました。この抗争は、地元の有力組織である双葉会会長の森田三千丈氏や、名古屋での山口組勢力の長老格である山口組直参の増田圭佑氏が動き、わずか4日で集結させたそうです。 - 同友会系鈴木組との抗争 (1983年)
1983年11月には、同友会系鈴木組と弘田組経過か山組によるトラブルが多発する中で起こった抗争が描かれます。同友会が世話をする愛知県のスナックで両組織の組員が喧嘩し、同友会系鈴木組組員が両親会組員3名を事務所に連れ帰って暴行を加えました。その報復として、暴行を受けた両親会組員と他の組員1名が鈴木組事務所を襲撃。鈴木組は日本刀や拳銃で応戦し、鈴木組組長を含む双方に重軽傷者が出ました。
弘田組解散、そして「弘道会」の誕生へ
1983年、豊山一家襲撃事件で懲役13年の判決を受けていた司忍氏が出所いたします。まるでその出所を見計らっていたかのように、翌1984年には日本中の極道社会を揺るがす山一抗争が勃発いたしました。
当初、広田武志氏は山口組ではなく、対立する一和会に参入しようとしたそうですが、周囲の説得もあり参加せず、弘田組を解散し引退を選びました。弘田組に残った多くの勢力は、司忍氏が新しく結成した「弘道会」に参加することとなります。
動画では、弘道会には食事もろくに取れない貧しい環境で育ち、ヤクザになるしかなかった者が多く、服役を厭わずケンカに参戦する気概を持っていたと語られます。山一抗争でもその気概が発揮され、長期服役を厭わず一和会をピンポイントで攻撃する行動によって、ヤクザ界での評判を上げていったとのことです。
山一抗争下の躍動と名古屋支配の布石
山一抗争が続く中、弘道会はその存在感を増していきます。
- 一和会系組織への強硬姿勢
1985年2月、一和会系後藤組の若頭、吉田清澄氏が連れ去られる事件が発生。六代目山口組若頭補佐、竹内照明氏らが関与したとされています。後藤組は吉田氏の解放を願い、警察に組の解散届を提出し、山口組本部に詫び状を送るという異例の行動をとりました。同年4月には、一和会系水谷一家傘下の隅田組幹部らが弘道会系園田組幹部らに連れ去られ、水谷一家に解散届を出すよう迫る事件も起きました。水谷一家がこれを拒否すると、報復として隅田組が弘道会系組員を連れ去り、双方に死傷者が出る激しいやり取りがありました。1988年には、一和会系花田組組長が札幌ですすきのの喫茶店を出たところで、山口組系司同連合の組員によって銃撃され亡くなる事件も発生しております。 - 名古屋の経済支配
1989年5月、五代目山口組が成立し、司忍氏が山一抗争での功績を認められ若頭補佐として執行部入りを果たします。この頃、弘道会若頭となっていた高山清司氏は、名古屋の繁華街である栄や錦で、飲食店などから毎月集める組合費の回収代行サービスを始めました。これは各組織が個別に行っていた手間とトラブルを避けられるとして評判を呼び、サービス料で利益が上がるため、バブル期には名古屋の繁華街のほとんどが弘道会の管理下にあったといいます。この頃には、弘道会の支配率は発足当初の18%から30%にまで上昇していたとの報告もございます。
地元組織の反発と中京地区の再編
弘道会の急激な拡大に危機感を抱いた地元の有力組織は、反山口組・反弘道会の同盟として、運命共同会、別名「中京五社会」を結成しました。これに対抗するかのように、弘道会は中京地区で山口組参加ではない露天商を集め、連合会を作ろうと試みます。
しかし、これに反発したのが、運命共同会の中核組織であったテキヤ集団の鉄心会でした。鉄心会の幹部数名が弘道会に入ろうとする動きに対し、鉄心会上層部はこれらの幹部を絶縁処分とします。弘道会はこの行動を挑戦状と受け取り、鉄心会への攻撃を画策、実行に移すのです。
1991年1月、弘道会への敵対姿勢を示していた鉄心会組員が襲撃され重傷を負う事件が発生。さらに、鉄心会系組長宅への銃撃や、鉄心会組長宅に出入りしていた企業舎弟2名が銃撃され命を落とす事件などが立て続けに起こりました。これらの襲撃は、弘道会直系の有力3団体から選ばれたヒットマンによるものだったとされています。この激しい抗争は、稲葉地一家総裁の池田賢一氏の仲裁により、わずか一ヶ月で和解が成立したといいます。
この抗争と和解を経て、中京地区の組織は大きく再編されることとなります。平井一家総裁の岸上剛氏と瀬戸一家総裁の渡辺恵一郎氏は、山口組直参となりました。一方、稲葉地一家、平野屋一家、三吉一家、同友会、そして同友会の内紛で独立していたハマケン組の残党は、次々と弘道会に加入。その結果、中京五社会は実質的に崩壊し、残った鉄心会のみが「一誠一家」と名を改め、稲川会の直参となったのでございます。ここに、弘道会による名古屋統一が成し遂げられたと言えるでしょう。
山口組の掌握へ – 盤石なる「弘道会体制」の構築
名古屋という一大拠点での地盤を固めた弘道会は、日本最大組織の中心へと進んでいきます。2005年、司忍氏が六代目山口組組長を継承。同時に、弘道会の若頭となっていた高山清司氏が弘道会二代目を継承し、さらに六代目山口組若頭に就任いたしました。
組長とナンバー2である若頭が同じ弘道会出身という、ヤクザ社会では異例中の異例とも言えるこの体制は、弘道会が山口組を掌握し、盤石な権力基盤を築き上げたことを物語っております。
その後も、2013年には高山氏が弘道会総裁に就任し、若頭であった竹内照明氏が弘道会三代目を継承すると同時に山口組直参に昇格。2015年には竹内氏が六代目山口組若頭補佐に就任するなど、弘道会の幹部が山口組の中枢を占める体制は強化され続けています。これは六代目体制に限らず、七代目、八代目の山口組を見据えた体制であるとまで言われております。
弘道会の強さの所以とは
動画の結びでは、現在の六代目山口組と神戸山口組の分裂においても、弘道会からの離脱者が少ないことに触れられています。その強さの理由として、単なる経済力だけでなく、この動画で克明に描かれた、全国統一に先駆けて名古屋を統一したという彼らの持つ自信と誇りが、組織を支えているのではないかと考察されております。
貧しい環境で育ち、服役も厭わない気概。抗争を経て培われた武勇。高山氏による経済力の確立。そして何よりも、司忍氏と高山清司氏という強力なリーダーシップのもとで築かれた結束力と戦略。これらが複合的に作用し、弘道会を斯くも強靭な組織へと押し上げたのでしょう。
ヤクザという世界は、我々一般市民にとっては遠い存在ではありますが、その組織の成り立ちや抗争の歴史は、時に社会の裏側を知る手がかりともなり得ます。この動画は、弘道会という組織の壮絶な軌跡を辿ることで、その強さの秘密の一端に触れることができる、非常に示唆に富む内容でございました。
皆様も、もし機会がございましたら、このYouTubeチャンネル「闇と光」さんの動画をご覧になり、弘道会の知られざる歴史に触れてみてはいかがでしょうか。
それでは、今宵はこれにて。ごきげんよう。
紫煙亭主人 敬白