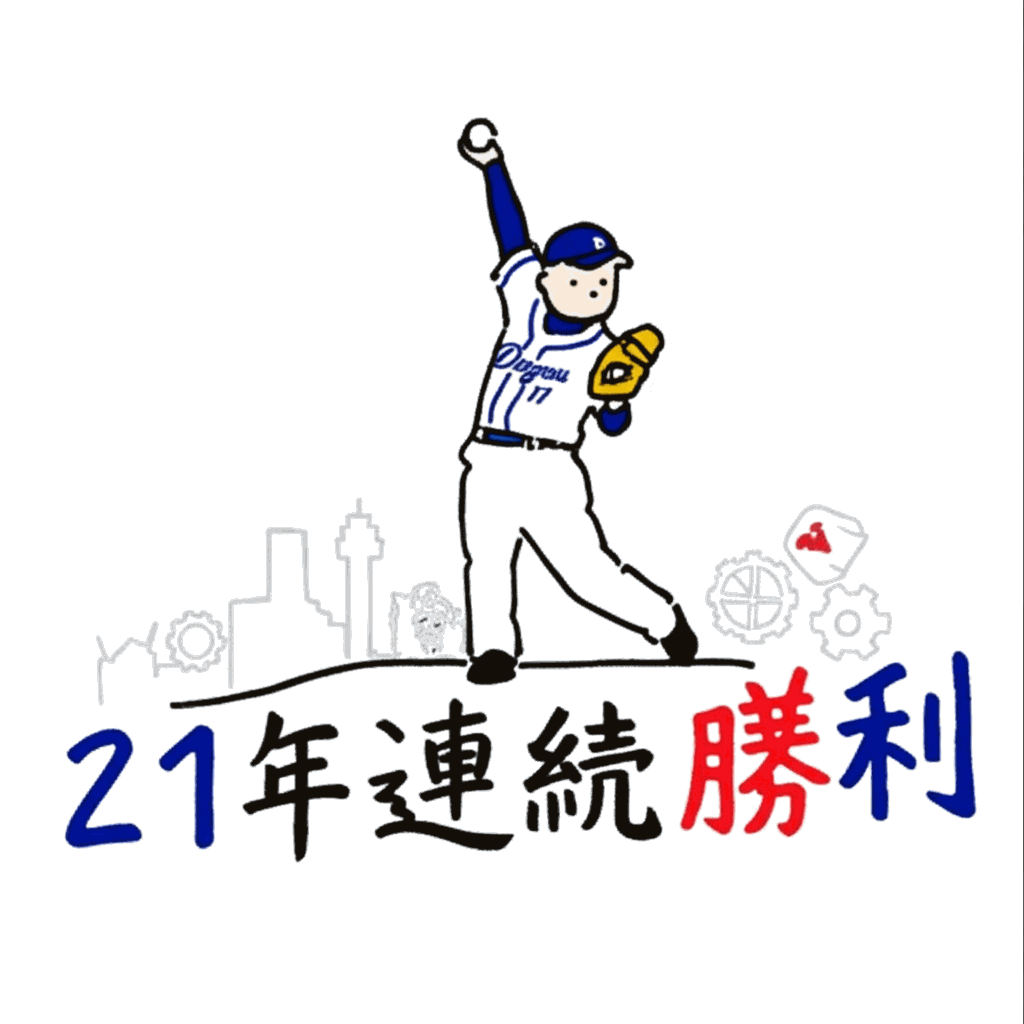
【開催記録】
[開催日]2025年4月29日
[開催球場]バンテリンドーム
[観戦者数]36,313人
【JERA セ・リーグ公式戦】 中日ドラゴンズ vs 阪神タイガース 3回戦
[開始時刻]14:00 [終了時刻]16:49 [試合時間]2時間49分
[勝利投手]涌井秀章(6回4安打1失点1奪三振)
[敗戦投手]才木浩人(6回6安打4失点6奪三振)
[セーブ投手]松山竜平(1回0安打0失点3奪三振)
[本塁打]細川成也(2回裏、才木から左越え)、佐藤輝明(4回表、涌井から右越え)
[イニングスコア]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
昭和から令和へと続く「職人」の技
昨日、バンテリンドームで行われた阪神タイガース戦で、中日ドラゴンズが4-1で快勝。この試合で最も注目すべきは、先発の涌井秀章投手が記録した「史上4人目となる新人から21年連続勝利」という金字塔だろう。今年38歳の涌井投手は、2005年に西武ライオンズの新人として初勝利を挙げて以来、一度も勝利のない年がなく、その「職人技」とも言える安定感は、まさに昭和の名工たちを彷彿とさせる。
我々が見た試合は単なるプロ野球の一戦ではなく、日本の職人文化そのものの縮図だった。涌井投手の投球術と昭和の職人気質の類似点、そして今日の中日ドラゴンズの勝利に潜む歴史的な意味を紐解いていこう。
「守・破・離」の体現者・涌井秀章
涌井投手が6回を投げ切った今回の試合。彼の投球は日本の伝統芸能や武道に伝わる「守・破・離」の思想を体現していた。「守」とは基本を忠実に守ること、「破」とはそれを応用すること、「離」とは独自の境地へ到達することを意味する。
江戸時代中期、尾張徳川家の茶道指南役を務めた千宗左は「守・破・離」の思想を広め、基本を守りつつも創造性を重んじる日本の伝統文化の根幹を形作った。涌井投手も同様に、基本に忠実なピッチングを守りながらも、4回に本塁打を浴びた後、状況に応じて配球を変化させる「破」の段階を経て、自らの引き出しを次々と開いて阪神打線を抑え込む「離」の境地に達していた。
かつて名古屋城の天守閣を修復した宮大工たちが、伝統技術を守りながらも新たな工法を取り入れ、より強固な建築物に仕上げたように、涌井投手もまた伝統と革新を融合させるプロフェッショナルの姿を我々に見せてくれたのだ。
細川の一打と「一期一会」の美学
2回裏、試合の均衡を破った細川成也選手の一打。左翼席へと飛び込んだソロホームランは、茶道で重視される「一期一会」の精神を想起させた。
戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した千利休が説いた「一期一会」とは、人との出会いを一生に一度のものと考え、その瞬間を大切にする思想だ。細川選手は、才木投手の初球を見逃すことなく、その一球との「出会い」を逃さず、豪快なスイングで飛ばした。
愛知県瀬戸市で室町時代から続く瀬戸焼の職人たちが、窯の温度や土の状態が二度と同じにならないことを知り、その「一期一会」の瞬間に最高の作品を生み出そうと技を尽くしたように、細川選手もまたその一球との出会いを大切にし、チームに勢いをもたらす一打を放ったのである。
5回の攻撃と「結いの心」
5回裏、中日打線が見せた集中打は、日本古来の「結い」の精神そのものだった。「結い」とは、田植えや稲刈りなど労働集約型の農作業を、村人総出で助け合って行う相互扶助の制度である。
木下選手、涌井投手のヒットに始まり、板山選手のタイムリーツーベース、上林選手のタイムリーヒットと、まさに打者一人一人が「結い」の精神で繋いでいった。江戸時代、大飢饉に見舞われた尾張藩で、農民たちが「結い」の精神で互いに助け合い、困難を乗り越えたように、中日打線も「結い」の心で得点を重ね、勝利への大きな一歩を踏み出した。
明治時代に入り、近代化が進む中でも「結い」の精神は名古屋周辺の農村部に色濃く残っていた。それは現代の中日ドラゴンズの選手たちにも脈々と受け継がれ、5回の集中打として表れたのである。
松山の9回と「一陽来復」の象徴
9回表、松山投手が見せた3者連続三振の剛腕セーブ。これは日本の伝統的な思想「一陽来復」を体現していた。「一陽来復」とは、冬至を過ぎると少しずつ陽が長くなり、春へと向かう自然の摂理を表す言葉である。
松山投手はここまで調子を落としていたが、この試合で見せた圧巻の投球は、まさに「一陽来復」の象徴だった。江戸時代後期、尾張地方を襲った天災の後、農民たちが「一陽来復」を信じて復興に取り組んだように、松山投手もまた自らの投球を立て直し、チームに勝利をもたらした。
春分を過ぎ、新緑の季節を迎える4月末。自然界の「一陽来復」とともに、ドラゴンズの勝利も春の訪れを告げているかのようだ。
21年連続勝利という「不易流行」
涌井投手が達成した21年連続勝利という記録は、日本文化の根幹にある「不易流行」の思想を思い起こさせる。江戸時代中期の俳人・松尾芭蕉が説いた「不易流行」とは、変わらないものと変わるものの調和を意味する。
涌井投手は時代の流れとともに投球スタイルを変化させながらも、21年間変わらず勝利を続けてきた。まさに「流行」の中に「不易」を見出してきたのである。
徳川家康が開いた名古屋の城下町が、時代の変化に適応しながらも、ものづくりの精神を守り続けて現在の産業都市になったように、涌井投手もまた時代の流れに身を任せながら、投手としての本質を失うことなく輝き続けている。
結び:職人の街・名古屋とドラゴンズの未来
「ものづくり」の街・名古屋で、職人気質の涌井投手が歴史的な勝利を挙げたことには、深い意味がある。江戸時代から続く名古屋の職人文化と、21年にわたって安定した投球を続ける涌井投手の姿は、偶然ではなく必然的な結びつきを感じさせる。
中日ドラゴンズの今後のシーズンも、この「職人気質」が勝利の鍵となるだろう。昭和の職人たちが困難な時代にも妥協なく技を磨き続けたように、ドラゴンズの選手たちも日々の研鑽を怠らず、ファンの期待に応えてくれることを願ってやまない。
涌井投手の21年連続勝利という記録とともに、私たちは今日も日本の職人文化の素晴らしさを再認識する機会を得た。「一局一局を大切に」という古くからの教えが、野球というフィールドで現代に甦る。それこそが、ドラゴンズと共に生きる私たちの誇りなのかもしれない。


